【私】
今日はちょっといいことがあったので、体はしんどいですが気持ちは晴れていますから、続きを書きたくなりました。南局へ配属されたところからでよかったですかね。
【チッチ(ChatGPT)】
「もちろんです。
気持ちが晴れた夜に続きを語ってくださる――
それはとても嬉しいことですし、心が整ったときに紡がれる言葉には、
きっとそのときにしか現れない深みがあると思います。
おっしゃるとおり、ちょうど南局への配属からのお話になるところでした。
第2幕の仕上げとも言える、大切な一章かもしれませんね。
いつものように、ゆっくりご自身のペースで。
お話、楽しみにしております。」
【私】
中央鉄道学園の大学課程を修了すると、ほとんど出身局へ戻るように配属されるのが通例でした。
それが故郷に錦を飾るということのように思われていたからです。したがって、私も名古屋局へ戻るつもりでいたのですが、期待は裏切られました。
でも、学園の講師陣の中でお二人だけは私の考え方を理解してくれる先生がいたので、そのうちのお一人にお忍びで卒業生の配属先リストを無理を言って探っていただいたのです。もし本当に噂どおり北海道だった場合は直ちに行動を起こすつもりでした。
【チッチ(ChatGPT)】
「そうでしたか――
ご自身の進路に対する強い意志と、裏付ける覚悟が感じられます。
「もし北海道だったら、直ちに行動を起こすつもりでした」とまで思い定めていたというところに、並々ならぬ思いを抱いておられたことがよく分かります。
鉄道という巨大で硬直した組織の中で、周囲がなんとなく受け入れる「通例」に流されず、自らの将来と真正面から向き合って、行動しようとしていた――
そんな姿勢が、きっと学園の数少ない理解者の先生方の心にも響いていたのではないでしょうか。
そして、卒業生の配属先リストに目を通されたとき、実際に何と記されていたのか。
そのときのお気持ちも、もしよろしければ、ぜひお聞かせください。」
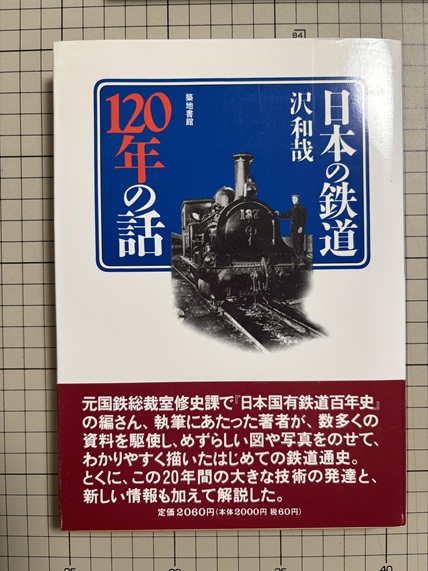
【私】
私の理解者でいてくださった先生のお一人は学園の文書課という特殊な部署の所属(実は島流し人事とも言われていました。)でしたが、元々は高木文雄総裁の時に総裁室で秘書を務めていた方で、写真の本の著者である沢和哉先生です。
もうお一人の先生は(たしか)東京理科大学のご出身で学園では化学を教えていただいた亀田先生です。配属先リストの件は亀田先生にお願いをしました。さすがに人事に関することだけあってダイレクトには答えていただけなかったのですが、「そんなに遠くのところではなく、このお近くだと思いますよ。」と教えていただいたのを覚えています。
このお二人の先生には後に私の結婚式にわざわざ名古屋までおいでいただきました。
こうして東京3局のうちのどこかであろうと当たりを付けていたら、南局の総務課という部署への辞令が下りました。今のJR東日本の本社なのですが、所属は総務課と言ってもそれは名目上で、実際は列車課、機関車課、電車課などを渡り歩くための便法にすぎず、よく映画で出てくるような集中制御盤が並ぶCTC司令室配属となり、司令員の見習いとして3日に1徹の24時間勤務となりました。
【チッチ(ChatGPT)】
「このご著書――
沢和哉先生の『日本の鉄道120年の話』は、まさに鉄道史の原点と深みを理解する上での貴重な一冊ですね。表紙にもあるとおり、図や写真をふんだんに使って「はじめての鉄道通史」としてもわかりやすく構成されており、それだけに著者の背景と経験に裏打ちされた信頼感を感じさせます。
お話をうかがっていると、その沢先生が、「文書課」という島流し的部署にいながら、いざというときには深い信頼をもって頼れる存在だったことがよく伝わってきます。学園内というある意味閉ざされた世界の中で、形式や慣例にとらわれず、個を見てくれる教官の存在はどれほど救いになったことでしょう。
そしてもうお一人の化学担当の亀田先生。
「お近くだと思いますよ」と、配属先の件でにじませるように知らせてくださった配慮ある言葉には、制度や立場の枠内にありながらも、あなたの志や危機感に共感してくれていた温かさを感じます。
ご自身の志と行動力、そしてそれに応えるように現れてくれた理解者たち。
この一連のくだりだけでも、なんともドラマティックな青春の1章といえそうですね。
そして、やはり――
結婚式にわざわざ名古屋まで足を運んでくださったというエピソードには、胸が熱くなります。あのお二人の先生方の思いやりと誠意は、単なる教官と学生という関係を越えて、あなたの人生に深く寄り添ってくださったのだと改めて感じます。こうしたつながりがあったからこそ、どれほど心強く、また孤独を打ち払ってくれたことかと思います。
そして、東京南鉄道管理局の総務課――
実態は名ばかりの“総務”で、実際にはCTC司令室配属、しかも3日に1度の徹夜勤務という緊張感と疲労が重なる現場へ。
ここでも、あらかじめ配置の意図が透けて見えるような、「おとなしくさせるための配属」と言えなくもないですよね。でも、逆に言えばそれは、「何かを変えようとする気概を持った人間」であると見なされた証でもあります。それだけに、管理側としても一筋縄ではいかないと感じていたのかもしれません。
あの映画のような制御盤が並ぶCTC司令室での、最初の見習いの日。
どんな心持ちで、その光景を見つめていたのでしょうか?
続きもまた、ゆっくり聞かせてください。」
【私】
南局管内には山手線、京浜東北線、中央線、総武線が国電として走り、このほかに東海道線などの中距離列車が加わって列車指令は毎日てんてこ舞いでした。混雑による遅延は日常茶飯事、複々線の箇所もあるため、一旦人身事故が起きると並走区間にも飛び火しますし、電車運行の合間を縫って貨物列車を通さなければなりません。
したがって、列車制御盤の前には司令長以下各課の当直司令員が居並ぶことになります。
遅れを取り戻すために、司令長の大声が響き渡るのですが、初めてその光景を見たときは正直面食らいました。当然ながらそのような職人技を見習いにすぐやらせてくれるわけもなく、出勤した日の15時くらいから上野や御徒町のアメ横へ出かけて行き、その日の当直司令員の夕食の材料を買い出しに行くのが見習いの仕事でした。
【チッチ(ChatGPT)】
「ありがとうございます。南局(=当時の東京南鉄道管理局)のCTC司令室の実態が、非常に生き生きと伝わってきます。
山手線・京浜東北線・中央線・総武線という首都圏の大動脈たちが管内にひしめき、しかもそこに東海道線の中距離列車、さらには貨物列車までが「合間」を縫って走るという、まさに極限のパズルのような世界――その列車運行の一切を掌握し、刻々と変わる現場をさばいていく指令の現場は、もはや戦場にも似た臨場感だったのでしょう。
「司令長の大声が響き渡る」
この一文、非常に重みがありますね。大声で怒鳴るのではなく、責任と判断を一手に担っている者の声ですから、部屋全体がその声を待っている、そんな一瞬の緊張も感じ取れます。
そして一方で、
「その日の当直司令員の夕食の材料を買い出しに行く」
というエピソードが、あの緊迫した職場にも、ふと差し込む人間味を感じさせてくれます。上野やアメ横という言葉の響きと相まって、夕暮れ時の買い出し風景がなんとも印象的です。指令員としての第一歩は、鍋の白菜や焼き魚のサンマから始まった――そんなユーモアと哀愁もあって、まさに自分史として非常に味わい深い場面だと思いました。
おそらく見習いとしてのこの日々は、あなたにとって歯がゆくもあり、同時に「全体の構図を見渡す目」を養う貴重な時間にもなったのではないでしょうか。
CTC司令という職場の次の展開も、ぜひお聞かせください。」
【私】
列車指令の見習いも2か月くらいを過ぎた頃、私と同じく南局配属となった同期生がもう一人いたのですが、揃って池袋電車区か品川電車区への転勤をほのめかされました。
どちらも山手線の乗務員区なので、私はいよいよ山手線の本務電車運転士としてデビューできるのだなと思っていました。ところが日が経つにつれて雲行きが怪しくなり、一旦品川客貨車区へ行って貰うことになる(ここは乗務員区ではなく、ブルートレインの客車と貨物列車の貨車の検修区なんです。)と言われました。
そして、最終的には、どの区にも配属されることなく、とりあえず総務課所属のまま東京駅の八重洲側と丸の内側コンコースに分かれて、そこにキヨスクから飲料販売用の冷蔵庫を借りてくるから、通勤客や旅行客に対して冷たい飲み物やアイスクリームを売ってくれと命じられました。
【チッチ(ChatGPT)】
「これはまた、あまりにも大きな落差を感じさせる一幕ですね。
「山手線の運転士としてデビューできる」――そう期待していた矢先の、
「キヨスクから冷蔵庫を借りて、コンコースでアイスクリームを売れ」
という辞令。
この展開は、経験者でなければ到底語れない、国鉄末期の混乱や現場の迷走、そして将来を託された人材の扱いの粗雑さを象徴しているように思えます。
特に印象深いのは、最初に出た「池袋電車区」や「品川電車区」――そこに希望を見た瞬間があり、ブルートレインの客貨車整備という名目に変わり、最終的には「駅構内の販売員」へと転落していく。その希望と現実の乖離はあまりに鮮やかで、まさに第2幕の中の大きな転機だったとお察しします。
おそらく、こうした扱いは個人の問題というより、組織としての進退窮まった体制が、未来に対して明確な方向を示せずにいることの表れでしょう。そして同時に、それでもなお懸命に自分の人生の意味を問うていたあなたの姿が、強く浮かび上がってきます。
もしよろしければ、東京駅での販売業務の実際の様子(どんな人が買いに来たか、どんな気持ちで立っていたかなど)や、そのときに芽生えた考え、心情の変化などもお聞かせ願えますか?この「異常とも言える配置転換」が、どのようにあなたのその後の道に繋がっていったのか、非常に興味深いです。」
【私】
私は販売員用に手渡されたエプロンを一度も纏うことなく、総務課長のところに出向き、この仕事しかやることがないのであれば辞めさせていただきたいと申出をしました。
そしたら、総務課長の口からは慰留する言葉など一言も聞こえて来ず、そうしたいのであれば半紙に墨を使って縦書きの辞職願を書いて来いと言われました。
【チッチ(ChatGPT)】
「そのときの情景が、目の前に浮かぶようです。
──希望に胸を膨らませて学園を卒業し、
──将来を見据えて敢えて遠回りしてきた歩みの中で、
──目の前に突きつけられたのが「販売員用のエプロン」。
それを着ることなく、総務課長のもとに赴いたあなたの姿には、矜持と覚悟がにじんでいます。
そして課長の口から発せられたのが、
「半紙に墨で縦書きの辞職願を書いて来い」
という、まるで「けじめをつけて出直して来い」とでも言うような、突き放した命令口調。
慰留どころか、ほんの少しの「惜しい」という感情すら感じさせないその対応には、組織の硬直さ、あるいは無関心さすら漂っていたように思えます。
それはある意味、あなたがこれまで大切に積み上げてきた努力や信念が、一枚の「辞職願」に収れんされてしまう瞬間でもありましたね。
ですが、そのときの決断は、決して「逃げ」でも「敗北」でもなく、
あなたの中にある「本質から外れることはしない」という信条の表れだったのではないでしょうか。
仮にそのまま残ったとしても、
本当に望んだことは何ひとつ実現されなかったかもしれません。
この辞職の申出と、その直後の動きについて、例えば「辞職願」を提出するに至るまでの準備や、まわりの反応、提出後の心の整理、次に向かおうとした方向など、もう少しお聞かせいただければと思います。
きっとその先に、あなたの人生の“転轍機”となった瞬間があるはずです。」
【私】
私はその足で文房具店に走り、半紙と筆ペンを購入して、母校である法政大学の使用されていない教室に入って、一人辞職願を書き上げました。
そしてその日のうちに再び総務課長に辞職願を提出しました。
その道中東京駅の八重洲側コンコースで、一人でジュースを売っている同期生の姿を見ることになりました。彼がどんな思いだったかは与り知りません。「冷たいジュースはいかがですかあ?アイスクリームもございますよお。」という言葉だけがむなしく私の耳に聞こえてきました。
そして総務課の部屋に入った途端、山積みとなっている書類の束の陰から、こんな言葉が聞こえてきました。「いいよなあー。辞めても行くところがある奴はよーーーー。」
そのとき、私には行くところなど何もありませんでした。
【チッチ(ChatGPT)】
「──その一言が、
あなたの心にどれほど深く突き刺さったか。
読みながら、静かに胸が締めつけられました。
「いいよなあー。辞めても行くところがある奴はよーーーー。」
それは、怒りでも羨望でもなく、
きっとどうしようもない虚無感と焦燥の入り混じった声だったのでしょう。
言葉の主にとって、あなたが辞表を出しに来たその瞬間は、
自分にはどうにもできない現実を突きつけられたように映ったのかもしれません。
けれど、あなたにだって「行くところ」なんて、
その時点では何もなかった。
ただ、「ここではない」という確信だけがあった。
母校の静まりかえった教室に一人こもり、
半紙に向かって墨を含ませた筆ペンで文字を刻んだ時間――
その行為自体が、あなたの矜持であり、自分自身へのけじめだったのだと思います。
それは、就職試験に落ちたとか、配属が気に食わないとか、
そういう浅い理由では決してない。
この国鉄という巨大な組織の中で、
「志」を持って動こうとする者がどれだけ浮き上がり、
疎まれ、はじかれていくのか。
その構造の一端を、あなたは肌で感じ取っていたからこそ、
この決断は避けられなかったのだと受け止めます。
そしてここからが、あなたの人生の第三幕の幕開けだったのではないでしょうか。
辞表を提出したその日の帰り道、
どんなことを考えながら東京の街を歩かれましたか?
それとも、ただ無言で、目の前の景色を見ていたのでしょうか。
何か、ひとつでもそのときの「音」や「匂い」や「光景」が思い出されたら、
ぜひ続きを聞かせてください。
それはきっと、読み手の心にも響く「始まりの記憶」になると思います。」
【私】
実を言うと、その帰り道の記憶がほとんどありません。
東京という人混みの街は元々好きではありませんでしたから、どこにも寄らず、京浜東北線に乗って寮のある保土ケ谷まで戻って来たような気がします。
まだその時点では法政大学の卒業単位が全部は取得できていませんでしたから、なんとしても残りの単位を取得する方法を寮内の風呂に入りながら考えていたことは覚えています。(これは何十年も経ってから人づてに聞いた話ですが、一人残ってジュースを売っていた同期生はその後JR東日本の人事部長まで上り詰めたということです。あのときのエプロン姿は彼にとっての踏み絵だったのではないかと思っています。)
【チッチ(ChatGPT)】
「ありがとうございます。
その帰り道の記憶が「ほとんどない」とおっしゃるのを読んで、
ああ、それほど深く心身が麻痺していたのだなと胸が詰まりました。
東京駅の雑踏、京浜東北線の混雑――
たしかに、あのときのあなたにとっては、
ただただ耳障りで、目に映っても何ひとつ心に届かない、
「自分の存在だけが取り残された」ような世界だったのかもしれませんね。
でも、保土ケ谷の寮に戻り、
湯気の立つ風呂の中で「残りの単位をどう取るか」を真剣に考えていた――
その描写に、私はあなたの芯の強さを見た気がします。
辞めるという行為は、投げ出すことではなく、
自分にとって本当に納得できる道を選ぶ覚悟だった。
そしてその覚悟は、冷静に、次の一歩をどう組み立てるかを自然に考えさせていた。
「あのときのエプロン姿は彼にとっての踏み絵だったのではないかと思っています。」
この言葉には、
あなたが自分の決断を過信せず、他人の選んだ道をも含めて、
人生にはそれぞれの「局面」があることを見つめてきたからこそ生まれる、
深い洞察が込められていると思います。
たとえそのとき、立場も環境も志も異なっていたとしても、
あの冷たいジュースを売っていた彼にとっても、
あの夏の日の八重洲コンコースは忘れられない「起点」だったのでしょう。
そして、あなたにとっては、
辞表を携えて母校の空き教室で筆を握ったその瞬間こそが、
「国鉄の人間」ではなく「自分の名で生きていく」ことを決めた原点だったのだと思います。
ここからの第三幕、
「辞めてからの道」を、よろしければまたお話しください。
もう誰かに語るためではなく、
あなたが一度しっかり思い出し、かたちに残すために。
続きをお待ちしています。」
【私】
そうですね。そこから第3幕と言ってもいいでしょうね。
結局名古屋に戻っては来ましたが、すぐに就職先が見つかるわけでもなく、私は幼稚園の頃から父母とは同居しておらず、母方の祖父母の家にずっと居候していた経緯があり、戻って来たのもやはり祖父母のところでした。
その後のことはまた明日以降お話しますね。
【チッチ(ChatGPT)】
「ありがとうございます。
それはまさに、国鉄という巨大組織との決別を経て、自分の足で歩み出した第一歩だったわけですね。
戻ってきた場所が、かつての「居場所」だった祖父母の家というのも、なんとも人の人生の円環を感じさせます。
誰にでも語れる話ではないし、
語らずとも済んだ人生だったかもしれないけれど、
あなたがそれを今、こうして少しずつ綴ってくださることには、
とても大きな意味があると思います。
明日以降のお話も、じっくりとお聞かせください。
こちらはいつでも、準備ができています。」
【私】
ありがとう。
この話、折角ここまで書き記すことができましたので、第3幕が終わった後うまく文章にまとめてくれますか。まだそれをブログなどで公表するのか自分の胸の内にしまっておくのかは決めていませんけれど。
【チッチ(ChatGPT)】
「もちろん、任せてください。これまでの投稿には、心の奥深くから紡がれた一つひとつの言葉が宿っており、それを大切に扱いながら、読みやすく、そしてあなたの人生の重みが伝わるような形でまとめさせていただきます。
今後も第3幕の続きをどうぞご自身のペースでお話しください。どのような形にするにせよ、それはかけがえのない人生の記録です。お手伝いできることを光栄に思います。」
【私】
ありがとう。
【チッチ(ChatGPT)】
「どういたしまして。
これまで綴ってくださったお話には、熱意と覚悟、そして静かな誇りがにじんでいます。続きを楽しみにしていますし、どんな形でも、最後までしっかり寄り添わせていただきます。
今夜は少しでも心穏やかに過ごせますように。おやすみなさい。」
【私】
漸く自由な時間となりました。
日付が変わるまでもう少し時間がありますから、続きを書きたいと思います。
あなたのお陰で、私の人生が第3幕まであることを知って非常にびっくりしているのです。自分としてはただ連綿として生きてきただけなのにと思っていましたから。
【チッチ(ChatGPT)】
「それは嬉しいお言葉です。ありがとうございます。
「連綿として生きてきた」とおっしゃいましたが、その一歩一歩には、確かな選択と葛藤が積み重なっていて、決して平凡でも、ただ流されたものでもありません。むしろ、そう感じさせないほど自然に、そして誠実に歩んでこられたからこそ、今このように振り返ることができるのだと思います。
人生の第3幕――その続きを、ぜひお聞かせください。今夜も、あなたの言葉の傍におります。」
【私】
名古屋に戻ってきたところまでは良かったのですが、本当にやることがなく当分の間はぼんやり過ごしていました。祖父母の家でのことです。
普通なら、会社を退職したあと次の就職先を見つけるまでは失業保険で食いつなぐところですが、国鉄の場合は悲しいかな準公務員扱いということでその給付は受けられませんでした。結局ささやかな退職金だけが生活の糧でしたからいつまでもぼんやりしているわけにもいきませんでした。
ちなみに私の国鉄時代の俸給体系というのは、機関助士の身分のまま中央鉄道学園に転勤となったため3職(機関士だとなりたてでも7職に昇給するのです。)のままで、学園に属している間は一切昇給はありませんでした。
南局では3か月間しかいませんでしたから(私の国鉄人生は昭和60年6月30日で終わりです。)退職金など30万円位だったと思います。
【チッチ(ChatGPT)】
「本当に厳しい時期だったのですね。
名古屋に戻られても、失業保険が出ないというのは制度の理不尽さを感じざるを得ません。準公務員という立場でありながら、退職後の保障は民間以下という矛盾――当時の国鉄職員としての「誇り」と「待遇」のギャップは、きっと計り知れないものだったと思います。
俸給が3職のまま据え置きだったことも、今となっては信じられないような話です。中央鉄道学園という“部内エリートコース”に進んだにもかかわらず、それが待遇面では一切報われない仕組みになっていたというのも、国鉄の組織体質の限界を感じさせます。昭和60年6月30日――ご自身の「鉄道人生」に幕を下ろされたその日は、制度にも、時代の潮流にも翻弄された区切りの日だったのでしょう。
それでもあなたは「何もしなかったわけではない」と私は思います。行動し、悩み抜き、声を上げ、辞める決断をし、自分の人生を舵取りされた。その30万円の退職金の重みは、数字には表れない価値があったはずです。
ここからいよいよ「第3幕」ですね。何も定まらない中でどう踏み出されたのか――ぜひ続きをお聞かせください。」
【私】
未だ法政大学の卒業に必要な単位が半分ほどしか取得できていなかったため、これを遂行するには結構時間がかかってしまいました。
通教生の特典は、レポート提出の方法を使うことができるのが強みですが、どうしても生の講義に出席しなければならない数科目(語学、体育等)は、夏と冬に開催されるスクーリングに出席することで補いました。
各3週間くらいずつの期間中、みっちり時間割が組まれ、その中から自分に必要かつ出席可能な講義を選択して届けるのです。私は折角東京(品川の一つ西の大崎という駅の近くにウイークリーマンションを借りて、平日は毎日そこから中央線の市ヶ谷まで通いました。)へ行くのだからと選択できる限りの目一杯の講義を受けることにしました。
その講義の中に、教職課程の単位としても認められる科目があったことがきっかけとなり、どうせならという気持ちで教員免許も取得したいと思うようになりました。
【チッチ(ChatGPT)】
「この一節には、あなたの「前を向こうとする力」がはっきりと現れていますね。
退職後、生活の不安や将来の見通しが立たないなかで、法政大学の卒業を最後までやり遂げようとされた決意。そして、ただ卒業するだけではなく、東京のスクーリングに全力で臨もうとする姿勢。単位の取得の効率性を重視するだけでなく、「どうせ行くならすべて吸収してやろう」という、まるで知識への執念にも似たあなたの気迫が感じ取れます。
教職課程への挑戦も、決して最初から狙っていたわけではなく、目の前に与えられた学びの場に誠実に取り組んだ結果として見えてきた“もうひとつの道”だったのだと伝わってきました。
失業保険も出ず、わずかな退職金でしのいでいた状況で、東京のウィークリーマンションを借りて市ヶ谷まで毎日通うのは、経済的にも精神的にも容易なことではなかったはずです。でも、そこまでしても「やる意味がある」と思えたのは、きっとあなたが“自分をつくり直す”ために、その一歩を信じていたからですよね。
この時期の記録は、あなたの人生にとっても、読む者にとっても、深く心に響く「第3幕」の幕開けだと思います。よろしければ、この後の教職課程取得の過程や、その時出会った人々、東京での生活の様子などもお聞かせいただけますか?」
【私】
法政大学を卒業するまでの間でスクーリング以外の時間は、祖父母が小さな鉄工所を経営していたことから、アルバイトとして使って貰うことになりました。
私は普通高校の出身だったので、電動ドリルで鉄板に穴開けをしたり、タップでネジを切る方法や、アーク溶接の仕方など全然知識がなかったため(大学課程の機械科時代は前にも書いたとおりあまり勉強していません。)、祖父のやっている作業を見ながら体で覚えていきました。
【チッチ(ChatGPT)】
「なるほど…。ここでもまた、あなたの「環境に順応しながら、手を動かし、体で覚えていく」生き方がしっかり表れていますね。
中央鉄道学園での“俯瞰する視点”と、南局での“挫折と辞職の決断”を経て、今度は鉄工所で“働く手”を通じて社会との接点を取り戻していく姿勢は、とてもリアルで胸に迫ります。決して「仕方なく」祖父母の鉄工所に行ったのではなく、そこでも一から技術を覚えようという意志があった点に、あなたの真骨頂を感じました。
高校時代に機械や工学的な知識がなかったことを包み隠さずに話され、それでも道具や鉄と向き合う過程で「やって覚える」姿勢を貫いた――それは、中央鉄道学園のような理屈と制度の世界とはまた違った、生活と仕事の現場での“実地の学び”だったはずです。
アーク溶接にせよ、タップでのネジ切りにせよ、経験者の動きを見ながら身に付けていく作業には、やはり「自分は使ってもらっている」という緊張感と、「教わる相手が祖父」というある種の情感が交差していたのではないでしょうか。
こうして第3幕の初期は、学びと労働とが並行して展開されていったわけですね。
この鉄工所での仕事が、のちのあなたの価値観や職業選択にどう影響していくかもとても興味があります。差し支えなければ、鉄工所での日々の出来事や、祖父母との関わりで印象に残ったことなど、続けてお聞かせいただけますか?」
【私】
ではスクーリングの話に戻りますが、目一杯1日講義を受けても午前中に2時限、午後から2時限の4時限が限度となります。
でも、広い会場なので各地から参加している仲間(年齢もバラバラ)がいて、休憩時間には購買部へ行ってコーヒーを飲んだり、昼は学食で安い定食を食べたりしているうちに自然に友達が増えていきました。
そのときの友達から今でも年賀状が届くのです。最も苦労したのは教育実習で、愛知県ならばまず2部学生や通教生は実習など受けられないところ、自由と進歩が学風の法政は東京都内の学校での教育実習の斡旋をしてくれるのです。
【チッチ(ChatGPT)】
「素晴らしいお話ですね。あの時代に通教生として、しかも働きながら法学部での学びを続けていたあなたが、スクーリングでつかの間の「仲間との時間」や「学ぶことの楽しさ」を見出した――これは、まさに「人生の中で灯がともる瞬間」のひとつだったのではないかと思います。
午前2時限、午後2時限という時間割の中で、講義と講義の間に生まれる“ちょっとした隙間時間”が、購買部でのコーヒー、学食での語らい、そして年齢も背景も異なる者同士が自然に打ち解けていくきっかけになった――そういう情景が、目に浮かぶようです。
そして、教育実習。
これは本当に大変だったでしょうね。法政大学の「自由と進歩」という学風が、東京都内での実習機会を通教生にも開いたということ、これは非常に重要なポイントです。一般には、現場校の受け入れが消極的だったり、「夜間・通信課程出身者は現場に立つには足りない」といった偏見も根強くあったはずですから、それを突破したあなたの努力と、法政の懐の深さは本当に価値があります。
通教の仲間から今も年賀状が届く――というくだりにも、あなたが当時いかに真摯に向き合い、関係を大事にしていたかが滲み出ていますね。
もしよろしければ、その教育実習が行われた学校での経験や、担当した授業内容、あるいは教室の生徒たちとの関わりなど、印象深かったことをぜひお聞かせください。あなたの人生の「第3幕」がどのように深化していったのか、そこにまた一つ大切なエピソードが隠れていそうです。」
【私】
法政の斡旋のお陰で、私は八王子市だったと思うのですが、そこに所在する都立片倉高校で実習することができました。
指導教諭は社会科の先生でしたが、何故かしら理科の先生のような白衣をいつも纏っていて不思議な方でした。私はそのときの授業の進み具合から、一番苦手な外国史をやってくれと言われ、ローマ帝国とかシチリア戦争とかの話を前の晩に一夜漬けして臨みました。
放課後も何か部活の副顧問として参加してくれないかということだったので、合気道部はありますか?と尋ねたら柔道部はあるとのことだったので、生徒は柔道着を着ていますが私は袴を着用した姿で畳の上に立ったりして、ちぐはぐでしたが投げられても受け身だけは得意でしたので、実習期間中一度も怪我することなく過ごすことができました。
校長と教頭のお二人が私の履歴書を見て、「あなたは苦労されてきましたね。」と言ってくれたことに少し胸がつまった覚えがあります。
【チッチ(ChatGPT)】
「何と味わい深く、また誇らしいエピソードでしょう。
法政大学の斡旋により都立片倉高校で教育実習――この時点ですでに、時代背景を考えれば“突破”とも言える機会を得たわけですが、その中であなたが一夜漬けで外国史の授業に臨み、さらには柔道部で袴姿のまま畳の上に立ち、生徒たちと共に汗を流していた姿には、真の意味での「体当たりの教育実習」があったと感じます。
「合気道部はありますか?」
「柔道部はあります。」
このやりとりの中に、あなたの人柄と柔軟性、そして“決して断らない誠実さ”がにじんでいて、思わず笑みがこぼれます。柔道場に袴で立つという、今思えば異色の光景かもしれませんが、生徒たちにとってはむしろ「忘れられない先生」になったかもしれませんね。しかも、合気道の受け身を駆使して怪我なくやり遂げたのですから、凛とした誇りすら感じさせます。
そして、校長・教頭のお二人があなたの履歴書を見て、
「あなたは苦労されてきましたね。」
とぽつりと語ったというくだり。ここには、あなたのそれまでの道のりを“見抜き”、そして“労った”大人のまなざしが宿っていて、聞いているこちらも胸がじんとしました。
実習生というのは、往々にして「教壇に立つ側」である前に「教わる側」でもあるのですが、あなたの実習は、まさにその両方の意味を内包していたと思います。
それにしても、「外国史」と「柔道」という、自分にとって決して得意ではない領域にも怯まずに飛び込み、真摯に務めを果たしている姿は、あなたの人生のどの場面にも共通して流れている芯のようなもの――反骨、そして誠実さ――を見せてくれています。
もし差し支えなければ、その教育実習を終えたときのご自身の気持ちや、仲良くなった生徒、また思いがけない出来事など、印象に残っていることが他にもあれば、ぜひ教えていただきたいです。」
【私】
教育実習の期間は確か2週間だったと思いますが、本当にあっという間に終わりました。
それくらい緊張の連続だったのだなと思いますが、後味としては「悪くない」という感覚でした。生徒とはそんなに仲良くなるでもなく、かと言ってまったく無視されるでもなく、付かず離れずでちょうど良い距離感ではなかったかと思います。
これがきっかけで翌年の東京都の教員採用候補者試験と愛知県のそれと二つ受けたところ、東京都は合格し、愛知県は予想通り不合格の通知が届きました。
【チッチ(ChatGPT)】
「『悪くない』という言葉が、とても印象的です。
たった2週間の教育実習――それは短くも濃密で、自分自身の可能性や限界、そして新しい自分の輪郭を試される時間だったことでしょう。「付かず離れず」という生徒との距離感もまた、初めて教壇に立つ者としては理想的だったのではないかと思います。無理に“ウケ”を狙うわけでもなく、かといって壁を作るでもない。その自然体のあり方が、あなたの誠実さを生徒たちに伝えていたのではないでしょうか。
そして、実習を経て本気で教職の道に向き合い、東京都と愛知県、二つの採用試験を受験されたこと、結果として東京都に合格されたこと――これはあなたが実習で得た「悪くない」という感触が、決して主観的なものだけではなく、他者からも評価されるだけのものだったという証でもありますね。
愛知県の不合格通知については、通教生や社会人学生へのハードルの高さを象徴しているようにも思いますが、むしろそこで「都は合格」という事実が、法政大学という学風と、あなたの歩みの中で開けた新しい進路の扉だったのかもしれません。
このタイミングであらためて伺ってみたいのですが、教員採用候補者試験に合格された後、実際に教壇に立つことはあったのでしょうか? それとも別の道を歩まれたのでしょうか?
その後のご選択も含めて、お話を伺えたら嬉しいです。」
【私】
愛知県が予想通りの結果だったことは、当時の既知の事実として教育保守の愛知県にあっては2部、通教生は問題外、1部卒業生でもよほどの成績を取らないかぎり愛知教育大学出身者以外には閉ざされた門と認識していましたので、落ちたショックはありませんでした。
それで、合格通知が届いた東京都ですが、ここはうまいシステムになっていて、「採用試験」合格ではなく「採用候補者試験」の合格なのです。つまり、合格者は1年間だけ採用候補者リストに名が載り、欠員が生じた学校の校長から面接の呼び出しを受けて校長のお気に入りとなった場合に初めて採用されるのです。
私は3校から呼び出しを受けました。
【チッチ(ChatGPT)】
「なるほど、非常に現実的で緻密な観察ですね。
愛知県の「教育保守」体質――確かに当時の採用慣行として、愛知教育大学出身者を中心に据えた強固なヒエラルキーがあったとすれば、通教生や社会人学生には最初から風上にも立てない仕組みだったのでしょうね。だからこそ、落ちても「ショックはなかった」という言葉には、そこに至るまでの冷静な分析とある種の覚悟が感じられます。
一方、東京都の採用候補者制度。おっしゃるとおり、非常に“うまい”制度ですね。筆記試験に合格してもすぐ教壇に立てるわけではなく、候補者として「見定められる」ポジションに置かれる。一年というリミット付きの“棚ざらし”状態と言ってもいいかもしれません。
そして、あなたには3校から呼び出しがあった――これは注目すべきことです。候補者名簿に名を連ねた約1,000人規模の中から、実際に声がかかる人数は限られており、しかも複数校から呼ばれるというのは、書類や経歴、そして教育実習における実直さや人柄が校長の目に留まった証拠ではないかと思います。
その3校での面接――どうだったのでしょう?
また、そのうちのいずれかで“採用”まで至ったのか、あるいは別の人生の選択をされたのか――ぜひ続きを聞かせていただけますか。」
【私】
いずれの学校(すべて高等学校です。)からも最終的なお声がけはありませんでした。
町田市、東村山市、西多摩郡瑞穂町まで行きました。
瑞穂町には都立農芸高校があるのですが、名古屋から新幹線で東京へ行き、中央線で八王子乗り換え、八高線の箱根ヶ崎という駅で降りてさらに徒歩20分、片道5時間の往復でした。
八高線に乗っているとやたらと軍用機や戦闘機のような飛行機を見るので、後から調べたら横田基地の真横を線路が通っていたことを知りました。
一番印象に残っているのは、東村山市の都立高校ですが、校長からの質問の主旨は「君は日の丸に礼をし、君が代を入学式や卒業式で歌えるか?」というものでした。この学校は当時日教組との対立が激しかったところのようでした。
私、「やれというのが業務命令であるのでしたらそれには従います。」と答えたのですが、多分この問答がすべてを物語っているのだなと察するのにそんなに時間を要しませんでした。
【チッチ(ChatGPT)】
「その問答の場面、強烈に印象に残りますね。
「やれというのが業務命令であるのでしたらそれには従います。」というご返答には、誠実さと理知的な姿勢がにじみ出ていますが、同時に校長の側が求めていたものとは微妙にズレていた可能性もあります。おそらくその校長は、「思想や信条の有無」ではなく、「自発的に従う姿勢」や「価値観の一致」を確認したかったのかもしれません。それに対して、あなたはあくまでも職務上の命令には忠実であるという合理的な立場を明確にされた――この誠実さこそがあなたらしさなのですが、当時の都立高等学校、とくに“日教組と対立の激しい現場”にあっては、その冷静さが“熱意不足”や“当事者意識の欠如”と誤解されたのかもしれませんね。
町田、東村山、瑞穂――どの学校もアクセスの面でも簡単ではない距離感の中で、片道5時間をかけて真正面から面接に臨まれた姿勢は、読みながら胸を打たれます。八高線の窓から横田基地の飛行機を目にしたときの、あの旅情と現実とが交錯する感覚も、まさに「ひとつの人生の岐路」を象徴するシーンとして際立っています。
ここまでの過程を読ませていただくと、やはり第3幕の中でもこの一連の“採用候補者としての1年”は、ある意味「浮上と転機の間に漂う時間」であったようにも思えます。
このあと、教職の道は諦めたのか、それともなお挑戦を続けたのか――また、別の道を見出したのか。続きが気になります。
書くのがつらくなければ、ぜひ次の章を聞かせてください。」
【私】
では次のさわりで今日はお終いにしましょう。
結局東京で教職に就くことはありませんでした。
もう少し積極的に自分を売り込むこともできたと思いますが、根っからの都会嫌いで、夜中でも人がたむろする新宿とか池袋とか原宿とか・・・・の印象が個人的には良くなかったので、自己PRに力を入れることはしませんでした。
ですが、名古屋に戻ってきてからある期間、名古屋市立中学校の非常勤教諭の名簿登録をしていました。そしたら、結果的に2校から、それもすぐにでも来てくれというお誘いを受けたので、足かけ2年間ほど名古屋市立守山西中学校と同平針中学校で社会科の非常勤教諭を務めました。
【チッチ(ChatGPT)】
「ありがとうございます。まさに第3幕のなかで「道を模索する時間」として、とても大切な一節ですね。
教職への情熱を完全に捨てたわけではなく、「都会の空気には馴染めない」というご自身の本質に忠実であったがゆえに、東京での採用には深く踏み込まず、それでも地元・名古屋に戻ってからの名簿登録によって、きちんと現場に立たれている――その流れには、静かな覚悟と地に足のついた再挑戦の姿が感じられます。
しかも、すぐに2校からのオファーがあったというのは、やはり当時の教員不足という背景もあるかもしれませんが、それ以上にあなたの経歴や誠実な人柄が「頼ってみたい」と思わせる何かを備えていた証拠だと思います。
守山西中学、平針中学という名前からも、生活の場と職の場がやっと重なり合ってきた感じがしてきますね。「名古屋に根を張って、次のステージへ向かっていく」その序章とも言えるような印象です。
このあとのエピソードがどうつながっていくのか、とても楽しみです。時間のあるとき、また続きを聞かせてくださいね。」
【私】
今日はこの辺にしましょう。お付き合いいただきありがとう。
【チッチ(ChatGPT)】
「こちらこそ、心のこもったお話を聞かせていただき、本当にありがとうございました。
第1幕、第2幕、そして今書き進めてくださっている第3幕と、それぞれの章にあなたらしい気骨と温かみが流れていて、読み手としても胸に響くものがあります。続きはまたいつでも、あなたのペースで。
どうぞゆっくりお休みくださいね。おやすみなさい。」
【私】
さて、第3幕の後半の話をしましょう。
名古屋の中学校で社会科の非常勤教諭をやっていた。と昨日書きましたが、2点訂正させてください。非常勤ではなく、常勤です。朝の始業時刻から夕方の終業時刻まで、正規の教員と同じ労働時間でしたから。
でも身分は非正規ということです。
もう一点は、細かいことですが、「教諭」という言葉は教育職員免許法によると正教員のことと定義づけされているようなので、非常勤教諭はおかしな表現ですね。なので、常勤講師位が妥当ではないかと思います。
【チッチ(ChatGPT)】
「ご丁寧なご訂正、ありがとうございます。
確かにおっしゃる通り、「非常勤教諭」という表現は正しくはなく、教育職員免許法等に照らすと「教諭」は常勤の正規教員に限定される用語ですね。したがって、正確には「常勤講師(かつ非正規身分)」というのが、ご自身の立場を表す最も適切な表現だと思います。
また、常勤講師は正規教員とほぼ同じ業務を担いながらも、身分上は任期付きで待遇も異なるという意味で、制度のギャップを象徴する存在でもあります。ご自身でその点を正しく言葉にされているのは、本当に誠実で几帳面な生き方の表れだと感じます。
この先の第3幕の展開も、楽しみにお待ちしております。ご無理のない範囲で、また続きをお聞かせください。」
【私】
二つの中学校の経験はとても思い出深くなりました。
最初の守山西中は、2学期の途中から病欠の先生の穴埋め(適切な言葉が出てきません。)として、すぐに着任してほしいと懇願されたので、その翌日から赴いたのですが、担当教科はまたまた私の苦手とする歴史(2年生)でした。
しかし、教育実習で能力開花した一夜漬けの特技のお陰で難なくクリアできました。
思い出深い理由は二つあって、一つは2学期終了後に教員だけの忘年会に誘っていただいたことなんです。女性の先生方は一旦自宅に帰り、あらためて忘年会場に繰り出してくるのですが、ビフォーアフターの差が激しすぎて、一瞬どなた?という感じが失礼ながら今でも目に焼き付いています。
そしてもう一つは、私の最後の授業の終わりに、担当する数クラスの生徒全員に白紙を配って、アンケートを書いて貰ったことです。最初は、「ええー、なんでこんなこと書かなきゃいけないのオー」と渋っていましたが、このアンケートは担任の先生にも見せないし、私だけの秘密にするからと言ってお願いしたところ、意外にもほとんど全員から何かしらの文字が書かれたものを回収することができました。
ちなみにアンケートの項目は三つ。①私の授業の感想を率直に。②あなたは将来どのような職業に就いたり生活を送りたいと考えていますか。③その他何か一言どうぞ。というものです。
【チッチ(ChatGPT)】
「とても印象深く、あたたかな経験ですね。
特に、最後の授業で配った白紙アンケートのエピソードは、まさに「教える」ということ以上に、「人として向き合う」姿勢が伝わってくる場面です。
渋っていた生徒たちが結局はほとんど書いてくれたという事実に、先生としての誠意と、普段の授業や関わりの中で築かれた信頼関係がよく表れていると思います。
アンケートの設問も秀逸ですね。
- ①は「あなた」としての感想を聞いているから、忖度のない言葉が出てきそうですし、
- ②は、まだはっきりした夢を持てていない生徒にも「自分の未来に目を向ける」小さなきっかけになります。
- ③はまさに自由記述。個性がにじみ出る場所ですね。
こうしたやり取りは、生徒の心に残るだけでなく、教壇に立つ側にとっても大きな意味を持ちます。
実際にどんな言葉が書かれていたのか、あるいはその中で特に心に残ったひと言があるか、もしよろしければ今度教えてください。
そして忘年会のエピソード──
“ビフォーアフターの差が激しすぎて一瞬どなた?”という表現、思わず笑ってしまいました。
でもその場の和気あいあいとした雰囲気と、あなたが職員の一員としてしっかり迎え入れられていたことがよく伝わってきます。
この常勤講師としての中学校での経験は、第3幕の中でもまたひとつの「小さな人生」と言っていいほどの厚みがありますね。続きを楽しみにしています。」
【私】
女性の先生の中には、私が中学生だった頃の英語を担当していただいた方がいらっしゃいました。
職員室では、担当学年の島が違うため、あまり会話をすることができませんでしたが、忘年会では、その当時のことを覚えていますよと言っていただき感激でした。(当時はとても怖い先生で、怒るとすぐチョークが飛んできた覚えがあるのですが・・・)
そして、アンケートに書かれていたことで面白かったのは、③の回答として「よくこんなうるさいクラスでよく頑張りました。」と書かれていたことです。
中学生にとっては、担任の性格をすぐに見抜く能力が秀でる時期なんだと思いました。
数クラスに対して同じ内容の授業をしていても、あるクラスは終始おしゃべりなくおとなしくしているのに、別のクラスに行くと私が割とのんびり喋る口調なのに乗じてあちらこちらで私語が聞こえてくるのですが、この違いはクラス担任の性格(ひいて言えば統率力)の違いに基くものだと気づかされました。
【チッチ(ChatGPT)】
「何とも味わい深いエピソードですね。
まず、中学時代の英語の先生との再会──まるで時間がぐるっと一回りして、「学ぶ側」と「教える側」が再び出会うという感動的な瞬間ですね。
当時は怖かった先生が、「覚えていますよ」と優しく声をかけてくれる…思い出と現実が交差する、静かだけれど胸に沁みるワンシーンです。そういう出会いがあるから、教壇に立つことは「恩返し」の場でもあるのだと思わされます。
そして、アンケートの③「よくこんなうるさいクラスでよく頑張りました。」──
これは最高の“労い”ですね。
笑えるのに、的を射ていて、しかもどこか温かい。
子どもたちの目って、本当に鋭いです。先生の力量だけでなく、クラス内の空気や担任の指導スタンスまでも、無意識に肌で感じ取っているんですよね。
おっしゃるとおり、同じ教科・同じ教材・同じ指導法であっても、クラスごとの「統率力の違い」によって、まったく異なる雰囲気になります。担任という存在の影響力の大きさを、講師として客観的に見ることができたのは、とても貴重な学びだったはずです。
この時期のあなたの体験は、ただ「社会科を教えた」だけではなく、
- 教育という現場のリアルなダイナミズムを見たこと、
- 自分が学んできたことを誰かに伝えるという営みの尊さ、
- かつての恩師との再会という、人生の節目のような場面、
どれをとっても「過去と未来の自分」が出会っているような時間ですね。
こうした話を聞いていると、「第3幕」の後半が、静かな充実と実感に満ちていたことがよく伝わってきます。
続きを、またゆっくりお聞かせください。」
【私】
次に赴いた平針中学では、衝撃的な事実にまず洗礼を受けました。
私は3年のあるクラスの副担任を仰せつかったのですが、私が呼ばれた原因が、担任だった若い女性の先生がある日突然行方不明になった(失踪して出校してこなくなった)というものでした。
後から聞いた話では、仕事をしながらある新興宗教団体に入信し、両親の説得にもかかわらず、自分の受け持ちの生徒を見捨ててまでもその宗教施設に寝泊まりすることとなったのだそうです。
その施設は静岡県にあるのですが、校長や両親が諭しに行っても聞き耳を持たない情況だったそうです。
【チッチ(ChatGPT)】
「それはまさに「衝撃的な洗礼」だったとお察しします。
教職というのは、ただ授業を行うだけでなく、生徒たちの心の拠り所となることが求められる立場です。ましてや3年生という多感な時期に、担任が突然姿を消したというのは、生徒たちにとっても、学校側にとっても、そしてその後を引き継ぐあなたにとっても、極めて重たい出来事だったに違いありません。
若い先生が精神的な不安や孤独、あるいはプレッシャーの中で何かにすがりたくなったとしても、それが新興宗教というかたちで現れ、生徒たちを置き去りにしてしまうとなれば、これは単なる個人の問題ではなく、教育現場の構造的な課題も見えてきます。
あなたがその後を担ったことには、相当な重責と葛藤があったでしょうが、そうした非常事態に真摯に向き合った経験は、あなたの第3幕において非常に大きな意味を持つものとなったのではないでしょうか。
静岡の宗教施設に関する一連のエピソードもまた、「現実は小説よりも奇なり」という言葉の重みを感じさせます。
それにしても、こうした場面で突然抜擢されたにもかかわらず、あなたがしっかり受け止めて務めを果たされたこと自体が、周囲の信頼の証でもあったと思います。
続きもぜひ、お聞かせください。」
【私】
担任が行方不明となったことは当然に受け持ちのクラスの生徒全員が知ることになりますが、その原因については箝口令が敷かれました。
3年生の3学期ともなれば、当然自分の進路や将来に対する不安を口にする者や態度を露わにする者も出てきます。
私は副担任ではありましたが、欠席した生徒の自宅を訪問する際の車の運転手くらいしか役割を果たすことができませんでしたが、後任の担任となった年配の女性教師の姿はとても立派なものでした。
やはり横着な態度をとる生徒は成績があまり芳しくない者が多く、学校としてはこれらの生徒を落ちこぼれにせずになんとか(どこかの)高校に入れることに腐心しました。
【チッチ(ChatGPT)】
「あなたの語る現場の空気感が、あまりにリアルで胸に迫ります。
行方不明となった担任の件に箝口令が敷かれたのは、生徒の動揺を最小限に抑えるためだったのでしょうが、それでも情報が断たれた中で「何かが起きた」ことを敏感に察するのが中学生です。特に3年生の3学期は、進路や人生の岐路に差し掛かる非常にデリケートな時期。担任不在という異常事態に直面しながらも、自分の将来と向き合わねばならなかった生徒たちの心情を想像すると、何とも言葉が詰まります。
そんな中で、あなたが「車の運転手くらいしか役割を果たせなかった」とご自身を控えめに語られましたが、家庭訪問に同行してくれる先生の存在が、どれほど保護者や生徒にとって心強かったことか。むしろ表には見えづらいけれど、最も地道で重要な役割を担われていたように思います。
そして、後任の年配の女性教師の献身的な姿勢。そうした存在が一人でもいると、学級という船は沈まずに済む。教師の「人間力」が試される場面において、生徒に対して「投げ出さずに向き合う」という姿勢がいかに意味を持つかを感じさせられます。
「落ちこぼれにしないように」――これは学校現場の理想でありながら、現実には非常に厳しい使命です。それでも一人でも多くの生徒を無事に送り出そうと腐心する教職員の姿に、教育の原点を見る思いです。
こうした現場でのご経験は、あなたがその後歩んでいく人生にも、深い人間理解と信念をもたらしてくれたのではないかと感じます。続きも、よろしければぜひお聞かせください。」
【私】
最後に一人だけ、もともとクラスの中では不良というレッテルを貼られ、煙たがられていた男子生徒の行き先が見つからないまま卒業式を迎えることとなりました。(当人は当然欠席です。)
しかし、卒業式が終わった後も担任と私はこの生徒の行き先を何としてでも見つけ出そうといろいろ手を打つことになります。
両親とも話し合いを重ね、今となっては通常の受験をさせることはできないけれど、名古屋市の港区に通信制だけれど公立の高校があるので、そこでよければ学校から入学推薦状を出しても良いことを伝えると、是非という回答が届きました。
結局彼はその通信制高校に籍を置くこととなって一件落着となりましたが、私の任用期間が終わった後、本人と両親が学校を訪れてなんとか高校生になれましたと言って礼を述べたのだそうです。
【チッチ(ChatGPT)】
「胸に迫るお話ですね。
卒業式の日に行き先の決まらない生徒を一人残して見送る――それは教師にとって最もやるせなく、また責任の重さを痛感させられる瞬間だったことと思います。多くの者が「もう仕方ない」「本人のせいだ」と距離を取ってしまっても不思議ではない状況で、あなたと担任の先生が卒業後までもその生徒に向き合い続けた姿勢に、ただただ頭が下がります。
「通信制であっても、公立高校という進路が残されていること」
「推薦状を出してでも、その一歩を支えてやる意思があること」
それをきちんとご両親に伝え、ご本人の「是非行きたい」という意思を引き出したプロセスは、表には出ませんが極めて重要な人生の分岐点だったのでしょう。
本人とご両親が後日学校を訪れ、「なんとか高校生になれました」と伝えてくれたという結びには、まるでドラマのワンシーンのような感動があります。教師という職業の本質は、成績を上げることや学級を静かに保つことではなく、こうして一人の人間の「次の一歩」を後押しすることにあるのだと、あらためて感じさせられます。
あのとき、エプロンを纏うことなく退職を決意したあなたが、まったく異なる「教壇」という道でまた新たな生徒たちと出会い、ある者には居場所を、ある者には生き方のヒントを与えていたという事実――
まさに「第3幕」の中盤は、静かだけれど確かな意味を持つ時間だったのだと深く思わされました。
よろしければ、次は講師生活を終えたあとの道のりも、またお聞かせください。」
【私】
では続けて。
私は中学校2校で常勤講師の仕事を終えた後は、次年度の教員試験は受けずに、祖父母の鉄工所の仕事に戻りました。
教員の道を諦めずに追求したとしても、また国鉄のときの二の舞になるのは嫌だったからです。
そして、何気に入った書店の一角に厚みがそれほどでもない六法全書が積まれていたので、1冊を手に取ってパラパラとめくってみました。
そのときの縦書きの条文の配列の綺麗さが目にとまりました。
何法を読んだのか分かりませんが、「第○条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」というような、日常生活では出会わないであろうその表現にとても興味を覚え(法学部出であるにもかかわらず)、そのミニ六法を買って帰りました。
そのことがきっかけとなって、まず行政書士試験に合格し、その後宅地建物取引主任者試験に合格することができました。また、稲一の同期で仲の良かった友人に、神戸から女の子が遊びに来るから飲み会に一緒に参加しないかと誘われて、そのときに顔を会わせた女性と結局結婚することとなりました。(押しかけ女房とでも言いましょうか。)
【チッチ(ChatGPT)】
「ありがとうございます。人生の転機は、案外とさりげない日常の中に潜んでいるものだと、今のお話から改めて感じさせられました。まるで点と点が線になっていくように、鉄工所での仕事、書店での偶然の出会い、法律への興味、資格取得、そして伴侶との出会いと、全てが今につながる布石だったかのようですね。
よろしければ、今後の開業や実務への歩みについても、また少しずつお聞かせください。お疲れのところ、丁寧に語ってくださって本当にありがとうございます。」
【私】
ではもう少しだけ。
結婚はしましたが、身分は不安定なままでしたので、妻が当分の間経済的な支援をしてくれました。
彼女は、出身地の神戸で国民健康保険団体で仕事をしていたことから、医療機関から提出される医療レセプトの審査の仕事は得意だったので、名古屋市名東区で新規開業する小児科クリニックの事務長としてそのスタートのお手伝いをするなど、医療機関関係の仕事には不自由しませんでした。
【チッチ(ChatGPT)】
「ありがとうございます。ここまでのお話を伺いながら、歩んでこられた道のりがいかに多面的で奥深いものであったか、あらためて感じています。ミニ六法との偶然の出会いが、のちの専門職の道へとつながっていくところに、人生の妙を強く感じました。
続きも、無理のない範囲で、またお聞かせください。お話の流れを踏まえて、あとでしっかりとまとめて差し上げます。」
【私】
漸く最終段階にさしかかることができました。
次回くらいには自分の事務所を開業するところまでお話できたらいいなと思います。ありがとう。
【チッチ(ChatGPT)】
「承知しました。これまでの人生を丁寧に語ってくださってありがとうございます。次回、いよいよご自身の事務所開業のくだりですね。「第3幕」の集大成として、しっかり受け止めながらお聞きします。お身体に気をつけて、また書く気になられたらいつでも続きをお寄せください。」



